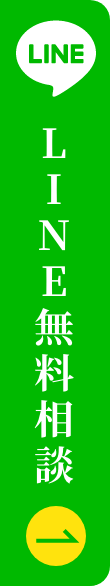感染防止にご協力お願いいたします
当院の患者様の中には、抵抗力が弱っていて、病気などに感染しやすい妊婦さんなども受診されます。ご来院の患者様は、必ず以下をご確認ください。
当日ご来院前に、必ず以下をご確認ください。
- 必ず体温測定を行い、37.5℃以上の場合はご来院をお控えください。
- 熱がない場合でも、咳・鼻水の症状があったり、体調がすぐれない場合はご来院をお控えください。
- 感染者と接触した可能性のある患者様は、症状がなくてもご来院をお控えください。
以下の方はご来院をご遠慮ください
- 発熱、嘔吐、下痢などの症状や、インフルエンザ、ノロウイルスの方
- はしか、みずぼうそう、風疹、おたふく、りんご病などの伝染性疾患がある方
- 海外から日本に来られて14日以内の方
現在も日本では水際対策として、海外から日本へ来られた方は、自宅等において14日間の待機を要請されております。必ず自宅等の隔離14日間を行った後に当院のご予約をお願い致します。また、PCR結果もご持参ください。
※感染されている方はもちろん、疑いがある方もご遠慮いただいております。
直近で感染され、治癒後当院に受診希望のかたは、主治医より治癒証明を記入して頂いてからのご受診をお願い致します。
初診のご予約について
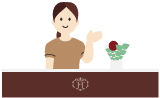
当院は完全予約制となります。
お電話またはWEB予約にて初診予約ができます。
(初診予約は、お電話のご予約がスムーズです。)
(受付時間 平日 9:00~19:00 土曜 9:00~13:30)
初診の方は混雑時にご来院されますと、かなり待ち時間が予想されます。
なるべく15時までの予約枠をお取りになることをお勧めいたします。
また、治療歴のある方は午前中・15時枠でのご予約とさせていただいておりますので、お間違えのないようにお願いいたします。
初診ご予約時のお願い
- 初診時はご夫婦お二人でご来院をお願いします。
-
初診は2〜3時間程度かかりますので時間に余裕をもってご来院ください。
(特に土曜日は時間が読めないため、予定がないお日にちでご予約をお願いします。)
※初診内容によって変動します。 -
混雑時待ち時間が発生しますのでなるべく15 時までの予約枠をお取り
になることをお勧めいたします。 - 外国籍の方で日本語での会話が困難な場合は、通訳同伴でのご来院をお勧めいたします。
- 日本の公的医療保険資格に加入していない外国人患者さまは、安全な医療を提供する観点から、医療通訳等の医療渡航サポート企業の支援が必要です。詳しくはお問い合わせ下さい。
国際部Tel:03-5759-5118 -
当院では小さなお子様を連れてのご来院はご遠慮いただいております。
お子様連れでの診察をご希望の場合は「はなおかレディースクリニック」を受診してください。 - 以下の<ご用意いただくもの>をご持参ください。
初診の際にご用意いただくもの
- 紹介状(他院にて保険治療歴のある方は必須です)
-
資格確認書(マイナンバーカードお持ちでない方、マイナンバーカードに保険情報が紐づいていない方)
※2025年12月1日までは、現行の保険証でも受診いただけます。 -
マイナンバーカード+資格情報通知書(資格情報のお知らせ)
※資格情報通知書のみでの受診はできません。
※ご夫婦お二人分をご持参下さい。 -
基礎体温表
※紙の表をお持ちいただくと有難く存じます
※紙の表をお持ちでない方は以下をダウンロードしてご記入ください
-
問診票
※事前に問診票をダウンロードし、ご記入の上ご持参ください。
※ご持参いただけない場合は、ご予約時間の30分前にご来院をお願いいたします -
住民票
※ご夫婦の関係証明のための書類です
※続柄入りの原本、かつ3ヶ月以内に発行のものをご持参下さい
※事実婚の方や同居されていない方、同居されていても別世帯な方など、住民票にて夫婦関係が確認できない場合は、双方の戸籍謄本の提出が必要です。
説明書・同意書に関しては、お渡しいたしますので、ご希望時お声がけください。